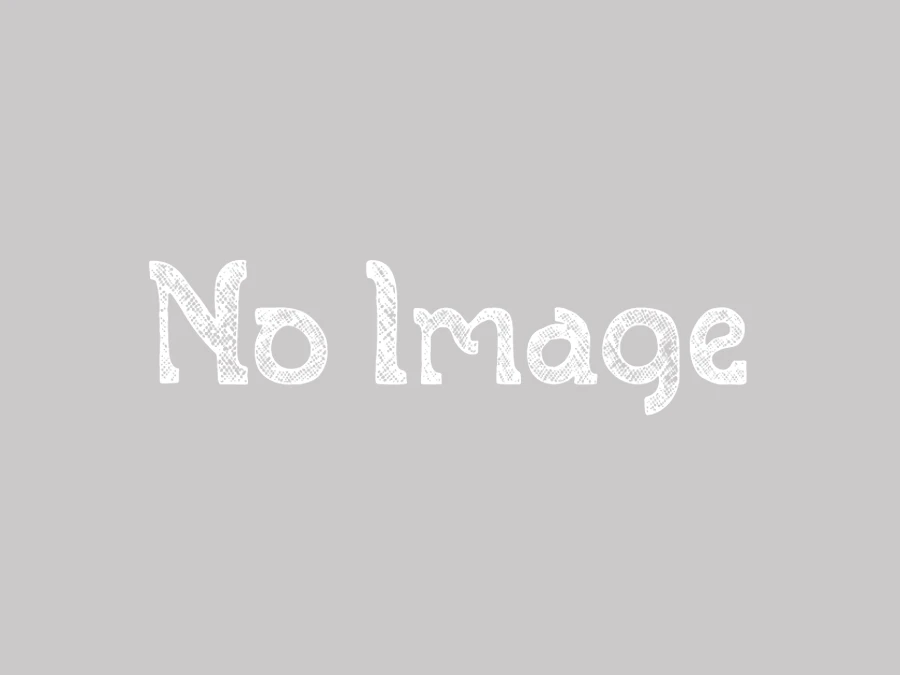国民車構想と大衆車のひろがり
昭和30年代、日本では自家用車のある暮らしが現実的なものへと変わっていきました。その背景にあるのが、1955年に通商産業省(現・経済産業省)が打ち出した「国民車構想」です。これは、誰もが購入できる価格帯で、燃費がよく、日常使いに耐える性能を持つ乗用車の普及を目指したもので、「最高速度100km/h以上」「価格25万円以下」などの目安が示されました。
この構想に刺激を受けて開発されたのが、富士重工業のスバル360です。1958年に発売されたこのモデルは、360ccエンジンと軽量なモノコックボディを採用し、手軽な移動手段として庶民の生活に浸透していきました。実際には最高速度は83km/h、価格は42.5万円で、国民車構想の目標をすべて満たしていたわけではありませんが、それでも初の“軽自動車の成功例”として画期的な存在でした。
その丸みを帯びた外観から「てんとう虫」と呼ばれ、フォルクスワーゲン・ビートル(かぶと虫)を彷彿とさせる親しみやすさも人気を後押ししました。さらに1961年にはトヨタが小型車「パブリカ」を発売。こちらは39.5万円という価格で登場し、低コストかつ実用性のある一台として、若い世代を中心に注目を集めました。
やがて日産や三菱、ダイハツといった他メーカーも相次いで大衆車を開発し、「マイカー」が家庭の現実的な目標として根づいていくことになります。
車社会と昭和のくらし
1960年代後半から1970年代にかけて、日本は高度経済成長の真っただ中にありました。所得の上昇と生活の安定を背景に、自動車の保有台数は急速に増加します。1966年には、トヨタ・カローラと日産・サニーがほぼ同時に発売され、同クラスでありながら異なる個性を持つ2台は激しい販売競争を展開。「カローラ対サニー戦争」と称される動きが市場を賑わせました。
性能・価格・サイズのバランスがとれた1000ccクラスの小型乗用車は、家庭向けとして最適とされ、全国で広く普及していきます。「マイカー元年」と呼ばれた1966年を境に、週末には家族でドライブに出かける姿が当たり前となり、観光地の駐車場にはさまざまな地域ナンバーの車が並びました。車は生活の一部となり、レジャーや移動の自由度を大きく広げる存在になっていきます。
一方で、自動車の普及が引き起こした問題もありました。特に深刻だったのが交通事故で、1970年には年間16,765人が事故で亡くなり、過去最多を記録。「交通戦争」とまで言われたこの状況は、当時の社会に大きな衝撃を与えました。
国産スポーツカーのはじまり
実用性を重視していた日本の自動車業界ですが、1960年代に入ると“走る楽しさ”にも焦点が向けられるようになります。そうしたなかで登場したのが、初期の国産スポーツカーたちです。
まず1963年にホンダS500が発売されました。二輪で培った高回転エンジン技術を取り入れ、小型で軽快な走行性能を実現。続いて1965年にはトヨタ・スポーツ800が登場し、軽量なボディと優れた空力設計で、ドライバーに新しい走行体験を提供しました。
中でも象徴的な存在が、1967年に登場したトヨタ2000GTです。ヤマハとの共同開発によって誕生したこのモデルは、美しい曲線を描くデザインと高性能を兼ね備えた本格的なグランドツアラーで、国内外から高く評価されました。生産台数は351台に限られましたが、今なお多くのファンに語り継がれる存在となっています。
この流れは1969年に登場したフェアレディZへと続きます。手頃な価格でありながら優れたパフォーマンスを誇り、北米市場でも大ヒット。こうして日本車のスポーツモデルは、世界市場でも確かな存在感を放つようになりました。