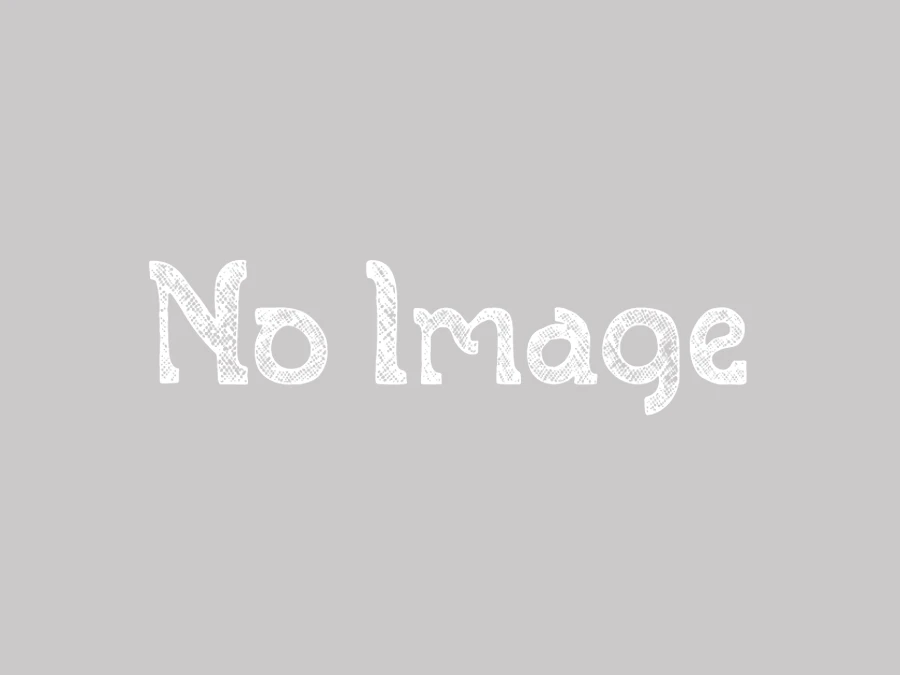免許制度が変わったタイミング
バイクに乗るための免許制度は、1975年と1995年に大きな変化がありました。1975年の改正では、それまで無制限だった自動二輪免許が排気量ごとに分けられ、「中型限定自動二輪免許」(400cc以下)や「小型限定自動二輪免許」(125cc以下)が新設されます。一方で、401cc以上のバイクに乗るには、試験場での実技試験に合格しなければならず、これが“限定解除”と呼ばれる狭き門となりました。
1995年には教習所で大型自動二輪免許を取得できるようになり、ハードルが下がります。それまで一発試験でしか取得できなかったために限られた人しか持っていなかった大型免許が、少しずつ一般にも広がっていきました。
こうした制度の見直しは、ライダーの裾野を広げるきっかけとなり、バイク市場全体にも影響を与えていきます。
大型バイクへのあこがれと現実
1990年代半ば、教習所で大型免許が取れるようになったことで、大型バイクへの関心が高まりました。それまでは高嶺の花だった750ccクラスや1000cc超のバイクが、現実的な選択肢として注目されるようになります。
特に人気があったのは、ホンダCB750やヤマハXJR1300、カワサキのZRXシリーズといった車種です。パワーやスピードだけでなく、重厚なフォルムや音の響きといった魅力が、若いライダーやリターンライダーの心を掴みました。
ただし、大型バイクには維持費や燃費、安全面でのハードルもあります。バイクそのものの価格も高く、装備や保険を含めると決して気軽な乗り物とはいえませんでした。あこがれを現実にできた人は一部に限られ、次第に250ccクラスの実用的なモデルが注目されるようになっていきます。
若者のバイク離れが進んだ理由
2000年代以降、若い世代のバイク離れが顕著になっていきます。その理由は1つではなく、いくつもの要素が重なっています。
まず経済的な負担が挙げられます。バイク本体の価格だけでなく、ガソリン代、駐車場、メンテナンス、保険料といった維持費も必要です。特に都市部では駐輪スペースの確保が難しく、車両を置く場所の問題も避けて通れません。
また、スマートフォンの普及や娯楽の多様化も大きな要因です。かつてバイクは“自由の象徴”として若者に人気がありましたが、今ではネットや動画など、別の形での楽しみ方が身近になりました。
さらに、安全性に対する意識の高まりも影響しています。交通事故のリスクや親世代からの反対など、バイクに対する不安感があることも事実です。
こうした背景から、バイクは“日常の足”というより“趣味性の高い乗り物”としての立ち位置が強まり、若者よりも中高年層の支持が目立つようになってきました。